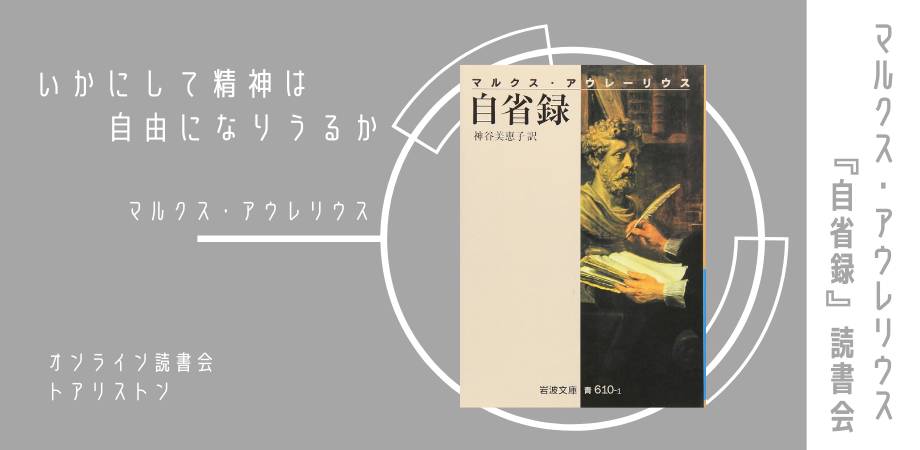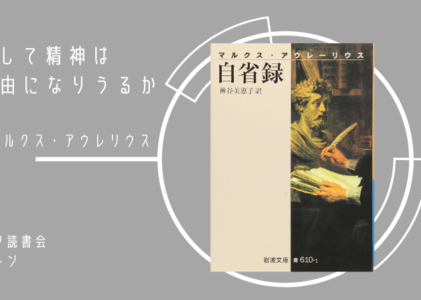・お申込みはチケット一覧ページから。
*読書会開始30分前までチケット購入が可能です。
*アーカイブが配信あります(チケット購入者にかぎり)。欠席されても安心な読書会です。
■哲学書にあまり触れたことのない人のための読書会
【哲学スクール】トアリストンの読書会メンバーの多くは、哲学書をあまり読んだことのない初学者です。
わからないこと、気になったこと、その場で考えたことなど、お互いに話しながら、ゆっくりと進行していきます。
真剣な会ではありますが、気軽にご参加いただける読書会になっております。
途中からのご参加も大歓迎です(本読書会の初回は2025年1月14日になります)。
特にマルクス・アウレリウス『自省録』は、一つの節が短く、それぞれの節の文脈も関係ないので、途中からご参加しても読むことができます。
■トアリストン読書会のご感想
・感想①
本当にお世話になりました。ゆっくりと、 納得がいくまで解説して頂けたので、理解ができたのと、 まとめながら整理できそのうえでわかっていけたことが大きかったように感じています。特に、後者のことは他の読書会ではあまり感じられない、 当読書会の特長と思います。 主催者の方の柔らかなイメージも哲学と良い意味で、新鮮かつ和やかな雰囲気で会が進んだことも個人的にとても心地良かったです。
・感想②
哲学書の原文を読むのは、小説と比べて難しく感じます。一文一文が重く、何を言っているのかすぐに理解できないこともしばしばです。ただ、誰かと一緒に読むと、自分では気づけなかった新しい視点や補足が得られることがあり、「そういうことだったのか」と腑に落ちる瞬間があります。一人で読むより時間はかかりますが、その分、少しずつ理解が深まる過程が面白いです。
・感想③
毎回、非常に丁寧に説明をして頂いているので解釈が深まります。説明用語もわかりやすいです。また、ところどころで主催者様が間に入り、他の参加者と意見交流することがありこれも思考が拡がるとともに興味がそそられるところです。そして、自分の解釈がまとまっていない場合でも、うまく整理し直していただけるので助かっています。加えて、受講者の意見を決して否定されないところは、安心感を得られるとともに本読書会の魅力であり、特長と思います。
■人生とは何かを考える―マルクス・アウレリウス『自省録』
本読書会では、第16代ローマ皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌス(121-180、在位161-180)の『自省録』を読みます(*)。
アウレリウスは五賢帝最後の皇帝で、『自省録』は忙しく責任のある職務のかたわらに書かれました。
哲学というと、日常から離れたことを考えるというイメージがあるかもしれませんが、『自省録』ではいわば人生論とも呼べる実践的な内容が書かれています。
彼は日常の自分を省みて、いかに生きるべきなのかを記録しているのです。
そこには、生から離れて宇宙の真理を探求する哲学ではなく、日々の様々な出来事に悩みながらも生きる理想を自らに問いかける哲学がありあます。
本書はそのため内容も馴染みやすく、哲学にはじめてに触れたい方にもおすすめの本となっております。
本読書会をきっかけに人生について考えてみませんか。
(*)マルクス・アウレリウスは後期ストア派に属する人物です。
後期ストア派(エピクテトスやセネカ、マルクス・アウレリウス)を中心とした格言集の読書会もやっております。
こちらの(『ストア派哲学入門』)読書会はより軽い読書会になりますが、後期ストア派を体系的に学ぶことができます。
『ストア派哲学入門』は、映画「ぼくたちの哲学教室」の、ケヴィン・マカリーヴィー校長の愛読書でもあります。
ぜひこちらもご参加ください。
■ト・アリストンと『自省録』
突然ですが、善く生きるとはどのようなことだと思いますか。
「成功哲学」という言葉があるように、努力して成功をおさめ、社会的な地位などを獲得することが善き生だと言えるのでしょうか。
アウレリウスはそのように考えていません。
地位や富そのものは、善いものでも悪いものでもないのです。
それらをもっていも悪人であったり、もっていなくても善人がいるようにです。
「死と生、名誉と不名誉、苦痛と快楽、富と貧、すべてこういうものは善人にも悪人にも平等に起こるが、これはそれ自身において栄あることでもなければ恥ずべきことでもない。したがってそれは善でもなければ悪でもないのだ」(『自省録』第2章11節、神谷訳、岩波書店、2007年)。
私たちは日常の渦に巻き込まれ、つい最高の善(ト・アリストン)について考えるのをやめてしまします。
地位や名誉、お金、長生き、快楽についてばかり考えてしまいます。
『自省録』は、そのような渦に取り囲まれながらも、最高の善を持とうとしたアウレリウスの姿を垣間見ることができます。
「正気に返って、自己を取りもどせ。目を醒まして、君を悩ましていたのは夢であったのに気づき、夢の中のものを見ていたように、現実のものをながめよ」(『自省録』第6章31節、神谷訳、岩波書店、2007年)。
とはいえ、実際にそのように生きることができるのどうか、など様々な疑問が湧いてくるかと思います。
ぜひ、本読書会を通じて、疑問に思う部分、自身の日常に当てはまる部分など、話し合うことができればと思っております。
心よりお待ちしております。
■イベント詳細
〇テキスト
・マルクス・アウレリウス『自省録』、神谷訳、岩波書店、2007年(事前にご用意ください)。
・本読書会では、24頁から読み始めます。『自省録』の始めの方は様々な人物への感謝が中心となっており、『自省録』の思想を把握したうえでないと、読むのが少し大変である(単なる感謝としてしか読めない)ためです。
〇日時
・隔週火曜日、20時~22時
〇期間
・読みえるまで
〇場所
・Zoomを用いたオンラインでの読書会になります。
・スマホやタブレットでのご参加の場合は事前にアプリのダウンロードをお願い致します。
・アプリのダウンロード方法がわからない場合、Zoomサポートにてご確認ください。
・パソコンでのご参加の場合はダウンロードは必要ありません。
・読書会を録画して、読書会のメンバーに2週間ほど共有しおります。予めご了承ください。
・録画動画はチケットをご購入していただいた方にかぎりお配りしております。
〇参加にあたって
・練習の場として、覚えたての知識を気軽に使っていただければ、 と思っております。
・体験ベースの読解も積極的にしていただければと思います。
・うまく論じることができなくても大丈夫です。 練習の場として考えていただければと思います。
・読解にある程度の一貫性をもたせつつも、 多様な読解可能性を保持できるように進んでいく予定です。 ご了承ください。
・自分の主張を無理に相手に押し付けたり、 相手を侮辱する発言をした場合ご退室いただきます。
〇その他
・参加人数が少なくなった場合などは、すべて読み終える前に読書会を終了する場合があります。 ご了承ください。
■読書案内
・岸見一郎『マルクス・アウレリウス 自省録 他者との共生はいかに可能か』(NHK出版、2023年)
→NHKの100分で名著シリーズです。非常に読みやすく簡潔でおすすめです。
・R.ホリデイ『ストア派哲学入門』(パンローリング株式会社、2017年)
→ストア派をより実践的に身につけるために書かれた、ベストセラーです。同書は、映画「ぼくたちの哲学教室」の、ケヴィン・マカリーヴィー校長の愛読書でもあります。
また、トアリストンでは、同書の読書会も開催しておりますので、ぜひご参加ください。
・荻野弘之、(イラスト)かおり&ゆかり『奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業 ――この生きづらい世の中で「よく生きる」』(ダイヤモンド社、2019年)
→マルクス・アウレリウスが大きく影響を受けた、後期ストア派エピクテトスの哲学を非常にわかりやすく解説した本です。
・國方栄二『哲人たちの人生談義 ストア哲学をよむ』(岩波新書、2022年)
→ストア哲学を、自由や運命などのテーマ毎に論じた本です。
・國方栄二『ギリシア・ローマ-ストア派の哲人たち-セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウス』(中央公論新社、2019年)
→ストア派の歴史的な背景まで扱った本です。より深くストア派について知りたくなったらどうぞ。
・荻野弘之『マルクス・アウレリウス『自省録』: 精神の城塞 』(岩波書店、2009年)
→マルクス・アウレリウスについてより詳しく勉強したくなったらどうぞ。
・マルクス・アウレリウス、(訳)水地宗明『自省録』(京都大学学術出版会、1998年)
→『自省録』のより新しい訳です。注も豊富でおすすめです(ただし、本読書会では、入手のし易さから、岩波文庫の訳を扱います)。
・A.A.ロング『ヘレニズム哲学: ストア派、エピクロス派、懐疑派』(京都大学学術出版会、2003年)
→本格的にストア派の哲学を勉強したくなったらどうぞ。
■講師
・西脇祐(中央大学):https://researchmap.jp/nishiwakiyu
・ホワイトヘッド哲学の発展史に関する研究者。最近では、ホワイトヘッドを中心とした20世紀初頭有機体論に関する研究も発表している。
■トアリストン
・ホームページ
https://toariston.tokyo/
・ツイッター
https://twitter.com/philotoariston
・スレッズ
https://www.threads.net/@ philotoariston
*当方は適格請求書発行業者ではないため、インボイス制度に対応した適格請求書の発行はできかねますので予めご了承ください。