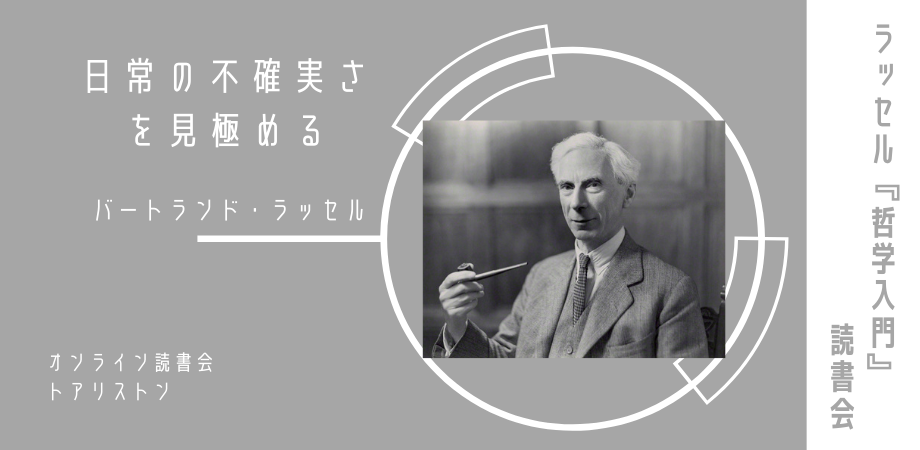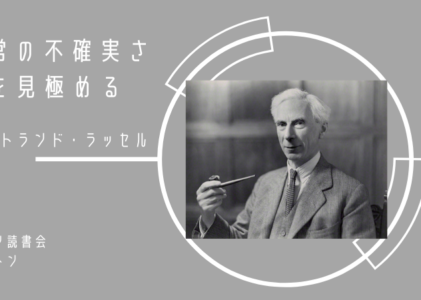2025年1月21日に第二十回 ラッセル『哲学入門』読書会がありました。
70頁の第三段落目「記述によってのみ…」から73頁の最後まで読みました。
今回はこれまでの議論をまとめつつ、記述による知識の根本原理を提示しております。
ある対象に関する会話ができるということ(70-1)
直接面識できない何か、すなわち記述によってのみ知られる何か〔例えばビズマルク〕について、私たちが語っている場面を考えてみましょう。
会話をしているときに、異なった表現を使っているのに、同じ対象について話している状況を、ラッセルは記述理論によって説明しようとします。
会話しているとき、日常的には、あたかもビスマルクそのもの(現実の事物)を含む表現ができていると私たちは考えてしまいます。
ところが、私たちはビスマルクを面識していないので、そのようなことはできないとラッセルは言います〔詳しくは67頁にも書いてあります〕。
それでは記述理論において、対象について表現をするときは、どのような状態になっているのでしょうか。
私たちは「ビスマルク」と呼ばれる対象Bがあること、そしてBは抜け目のない外交家だったことを知っているので、主張したいと思っていた命題―ビスマルクをBという対象とした場合の「Bは抜け目のない外交家だった」―を記述することができるのである。
ラッセル『哲学入門』高村訳, 筑摩書房, 2005年, 71頁
「ビスマルク」と呼ばれる何らかの対象があること、そしてそれに関する特徴を知っているからビスマルクに関する命題をつくることができ、「互いに異なる記述を用いているにも関わらず、会話することができる」(ラッセル『哲学入門』高村訳, 筑摩書房, 2005年, 72頁)のです。
例えば、「ドイツ帝国の初代宰相」という異なった記述をしたとしても、「ドイツ帝国の初代宰相だった現実の対象について、それは抜け目のない外交家だったと主張する命題」(ラッセル『哲学入門』高村訳, 筑摩書房, 2005年, 72頁)を記述することができます。
しかし、とラッセルは言います。
私たちが関心を持つのはこの命題―記述されている、そして正しいことが知られている命題―なのだが、しかしこの命題そのものを面識してはいない。またそれが正しいということは知ってはいるのだが、その命題そのものを知らないのである。
ラッセル『哲学入門』高村訳, 筑摩書房, 2005年, 72頁
私たちは日常会話で、様々なに異なった記述をします。
ラッセルは正しい命題が事実のように存在しているといいます。そして、それが正しいことを知っているのだけど、直接私たちは面識していない状態であるといいます。
直接それを知っていたら、会話という動的な営みはなくなってしまうでしょう。
このような状態であるからこそ、私たちは一つの対象について様々な方向から考えることができるのです。
とはいえ、なかなか解釈の難しい段落で、命題が存在すると主張できる理由など詳しく論じてほしいな、と感じました〔この注ではこの時期はすでにラッセルは命題が存在するという立場にはないが、便宜上そうしていると書いてあります〕。
より詳しい説明は、野矢茂樹『言語哲学がはじまる』の166-71頁を参照してみてください。
記述を含む命題の根本原理(71-3)
これまでの議論をまとめつつ、ラッセルは記述に関する根本原理を定義します。
面識される個別的なもの(particulars)から知識はじまり、段階的に遠ざかっていく記述による知識を想定することができます。
〔補足:
邦訳ですとparticularsは個物や個体(69頁)となっており、経験における対象と私は読解していましたが、原文だとparticularsになっているため、端的に面識される特定の事柄といったニュアンスがいいのではと参加者にご指摘頂きました。
64頁では、動詞などの普遍に関わる議論で、面識されるものは個別的(particular)なものに限定されてはならないとも書いてあります。〕
例えば、直接ビスマルクに会った人は、ビスマルクについてのセンスデータ(個別的なもの)から記述をつくります。そして、歴史を通じて彼を知る場合、鉄仮面をかぶった人〔バスティーユ牢獄に入れられたが身元がわからないように、常に仮面を被っていた人物。その人物について本当のことはわからないけど、論理的に導かれる以上のことを知っている〕、最も長生きした人〔論理的な事柄しか導かれない〕と、これまでの議論を振り返りつつ、記述される対象が、特定の人物から遠ざかっている〔ある対象に関する、諸々の個別的なものに対する指示が希薄になっている〕ことを確認します〔そしてこのことは普遍にも当てはまるといいます〕。
このように記述による知識は段階をもちつつも、次の根本原理を充たさなければならないとラッセルはいいます。
理解可能なすべての命題は、面識されているものだけを要素とし、構成されているのでなければならない。
ラッセル『哲学入門』高村訳, 筑摩書房, 2005年, 73頁
私たちは直接面識していないものを、記述によって知識としてもっています。
しかし、そのような記述も、面識されているものだけを構成要素としなければならないのです。
私たちは記述による知識によって、けっして経験しないものを知ることができる。直接経験できる範囲が非常に狭いことをみるなら、記述がもたらすこの成果は死活的に重要になる。そしてこのことをが理解されないかぎり、知識の大半は神秘的で、それゆえ疑わしいものにとどまらざるをえないのである。
ラッセル『哲学入門』高村訳, 筑摩書房, 2005年, 73頁
極端な主観的観念論ですと、直接知られるもの以外は幻想となってしまうのでした。
ラッセルは経験主義的な立場に立ちつつも、直接知られないものに関する知識の構造についてより建設的な議論を形成しようとしたのです。
おわりに
今回は記述による知識をみました。
第六章からはそのような知識にかかわる一般原理の吟味になります。
直接面識されないものの知識には何らかの推論形式(一般原理)が関わっております。
これまでどのような一般原理が用いられ知識が形成されてきたのか、その原理はどれほど信頼の足るものなのか、このことが吟味されていきます。
・開講中の講座
・過去の講座
・哲学史を学んだことのない人のための入門書案内
←哲学をするには基礎知識を摂取する必要があります。読書会でも丁寧に解説しますが、まとめて知識を得たいという方はこちらを参考にしてみてください。
X(旧Twitter):https://twitter.com/philotoariston
Threads:https://www.threads.net/@ philotoariston